今週の松竹梅第626号「税務調査で重加算税を避けるべき理由」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】
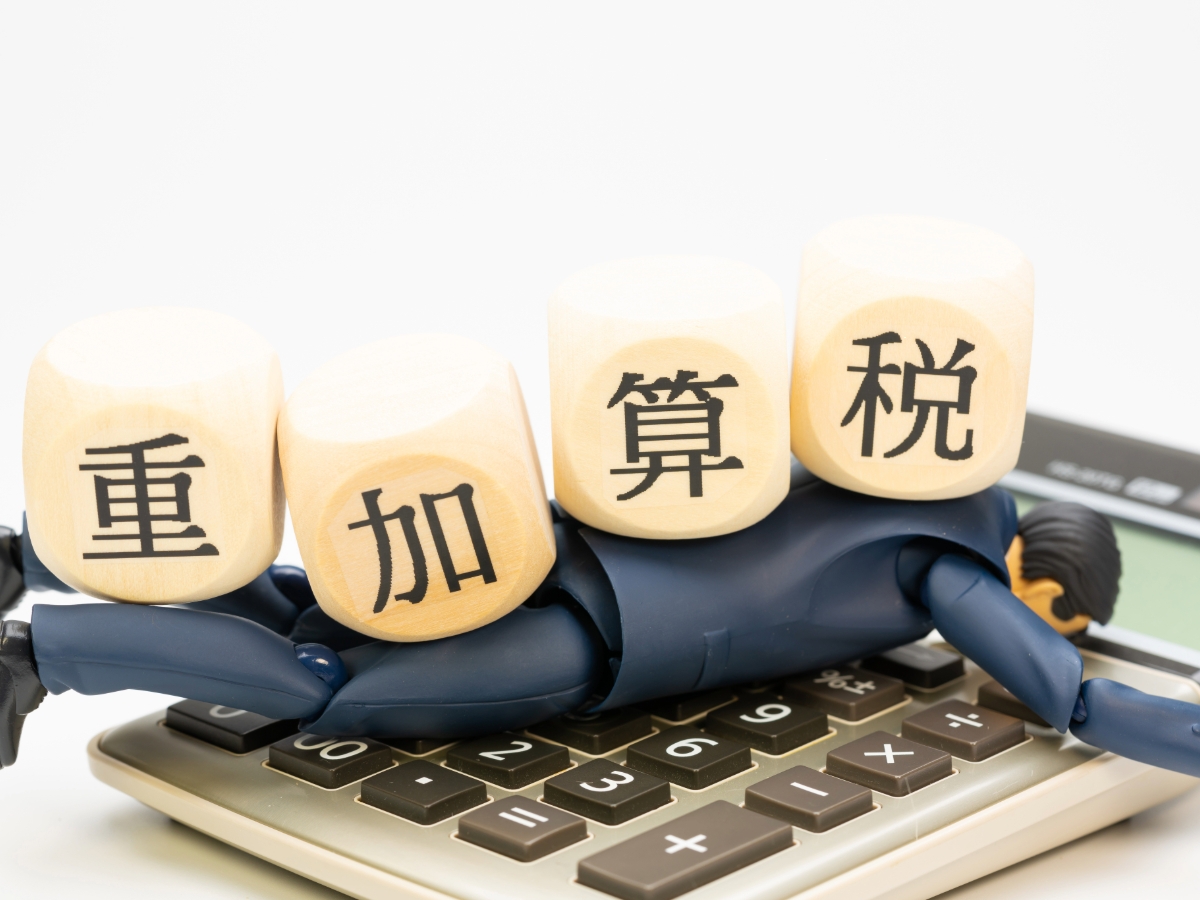
配信日:2025年7月7日
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第626号を配信します。 前々回からこのメルマガで法人税務調査を取り扱っており、今回は第3回です。 今回は「重加算税」についてです。私はここ数年は重加算税案件がないのですが、法人税務調査で修正事項を指摘され、重加算税扱いになる割合は例年およそ2割です。 重加算税の要件を考えると、2割は少々現場感覚とずれがある高い割合です。 不正=重加算税ですから、経営者はそんなに不正をしているのか!と考えてしまいます。 今回は、この深刻な事態の背景を理解して、重加算税を避ける方法を学んでいただきます。
【今週の松】 【今週の松】「調査件数と不正割合」
国税庁発表の統計数値によると、2024年6月までの事務年度で実施された法人税務調査は5万9千件、うち修正事項があった件数が4万5千件、そのうち「不正」があった件数が1万3千件、不正割合は22%でした。
この統計で驚くポイントは2点あり、年間の法人税務調査件数が意外と少ないのと、不正割合が異常に高いのでは?です。
ちなみに、法人税申告件数は313万件です。申告件数で考えると、2%割れですね。
また、税務調査での「不正」は、「うっかり」ではなく、「わざと」売り上げを抜いたり、架空外注費を計上したりなど、かなりハードルが高いのです。
それで不正割合22%はいくらなんでも異常値だと私は考えています。
【今週の竹】 【今週の竹】「なぜ不正割合が高くなるのか?」
この話題の前提ですが、「不正」と認定されると、重加算税の課税対象になります。 重加算税は本税に加えて35~40%追加で課税されます。これだけではなく、延滞税も高くなりますし、次の調査で重加算税が課税されるとさらに10%上乗せされます。 税額だけでなく、重加算税対象法人は、税務署内のグループ分類でランクが落ちて、明らかに何度も調査対象になります。担当調査官も特別調査官チームなど、やる気満々の方々が担当になります。一方で、税務署内の評価でも、重加算税を課税することは大きなプラスなのです。100万円のミスより、10万円の「不正」を見つける方が評価は高くなることもあります。 であれば、「不正」の定義が拡大解釈になるのは必然だと思いませんか?
【今週の梅】 【今週の梅】「重加算税の要件は仮想隠蔽行為!!」
不正=重加算税対象かどうかは、実にシンプルです。 会計処理の間違いが、「仮装隠蔽行為だったかどうか」のみです。 しかも、これまでの税務裁判では、仮装隠蔽行為は、「外部からもうかがい得る特段の行動があるかどうか」を要件としています。 これをよく理解していれば、不正割合22%はあり得ない数値です。 あえてわかりやすく言うと、調査官が重加算税案件にするために、「売り上げ抜いた?」「個人的な経費をわかってて経費にした?」「請求年月日書き換えたよね?」「取引先じゃなくてお店の女性と飲んだ?」などと言われて、認めてしまったと推察します。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「私の本領発揮は実地調査後の検討段階で」
私は税務署側と争うつもりもなければ、けんかするつもりもまったくありません。 ただし、修正事項を受け入れる場合は、とことんまで粘りまくりごねまくります。笑 調査スタートの挨拶では、ありありと、「おっ、当たりやん」との調査官の顔色は、実地が終わり検討段階で、私がごねまくると、次第に私を避ける雰囲気になります。 これまでも、連絡先が上司から若手に変わった事例が複数ありました。 揉めてる最中に発見した有利な採決事例を見つけると、税務署に行って調査官の前で朗読したこともあります。(怖い) それでは、次回もよろしくお願いします!

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版